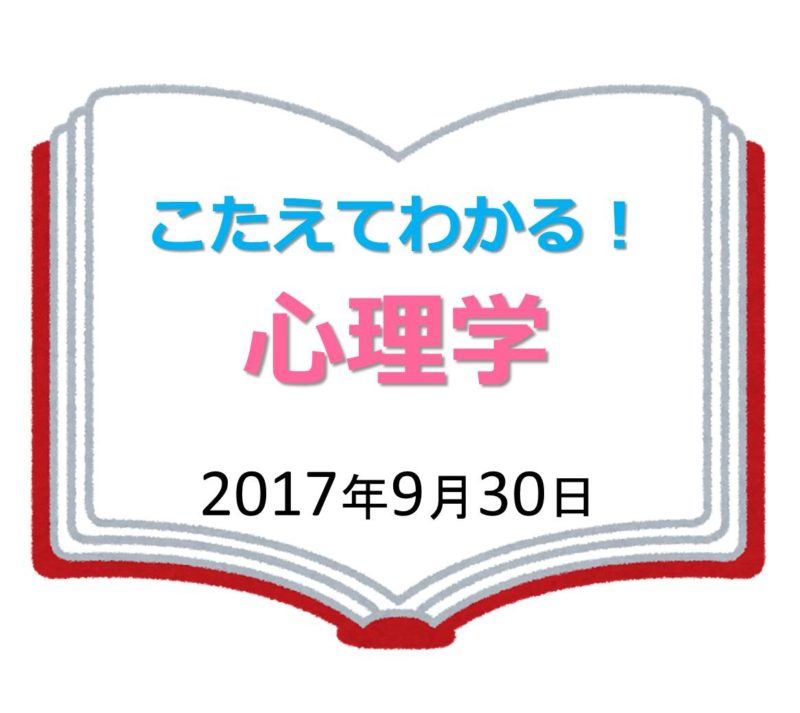◆「深層心理テスト」はなぜ「当たる」のか!?
日本の大学生67名を対象に、次のような実験が行われました。まず、ある市販の「深層心理テスト」の本に載っているテストを使い、実験参加者に回答を求めました。次に、本来の診断結果ではなく、ひとつずつずらした診断結果(つまり、デタラメな診断結果ということになります)を示しました。そして、実験参加者に、その診断が「当たった」かどうかについて5段階で評価してもらいました。
集計の結果、「非常によく当たった」と答えた人と「当たった」と答えた人の合計人数は、全体の約50%を占めていたということです。これはかなり高いヒット率だと思いませんか?
ではなぜ、こういった簡単な、いわゆる「深層心理テスト」について、50%もの人が「当たった」と判断してしまったのでしょうか。
ひとつめのポイントは、診断結果が「断定を避けた曖昧な言い方」であることです。曖昧でどのようにもとれる診断だからこそ、誰がどの診断を見ても「当たった」と思いやすくなります。これが「深層心理テスト」が「当たる」第一の理由です。
ふたつめのポイントは、診断が「誰にでもあてはまる」ことを述べている点です。例えば、私たちは誰でも、イライラすることもあれば、しないときもあります。ですから、「イライラすることもあるが、それなりに安定した毎日を過ごしている」といった「診断」は、多くの人に当てはまることを述べているだけなのです。したがって、誰が6つの「診断」のどれを見ても、「そのとおりだ」と判断しやすくなります。これが第二の理由です。
なので、こういった「深層心理テスト」はエンターテイメントとして楽しむのがいいのかもしれませんね。
心理学で使われる「性格検査」や「知能検査」は、こういったエンターテイメント性を持った「深層心理テスト」とは違います。その違いは、「根拠があるかどうか」です。また、心理検査は「深層心理」を言い当てるために作られているのではなく、検査結果を通じて、その人の現状を把握したり経過を観察したりすることが目的です。
心理学科の授業では、根拠に基づいて作成された心理検査や心理尺度を体験することができます。自分を知るきっかけになるので、やってみるとおもしろいものです。
オープンキャンパスでも、「恋愛テスト」のコーナーでは、多くの人の調査データにもとづいて作成された心理尺度を体験していただけます。興味のある方はぜひお越しください!
本日この企画に参加してくださった方の回答の割合は、翌週アップします!(^^)
引用文献
境敦史(2008).「深層心理テスト」は、なぜ「当たる」のか 境敦史・小貫悟・黒岩誠(編著)心理学に興味を持ったあなたへ――大学で学ぶ心理学―― 学研教育出版 pp.16-27.