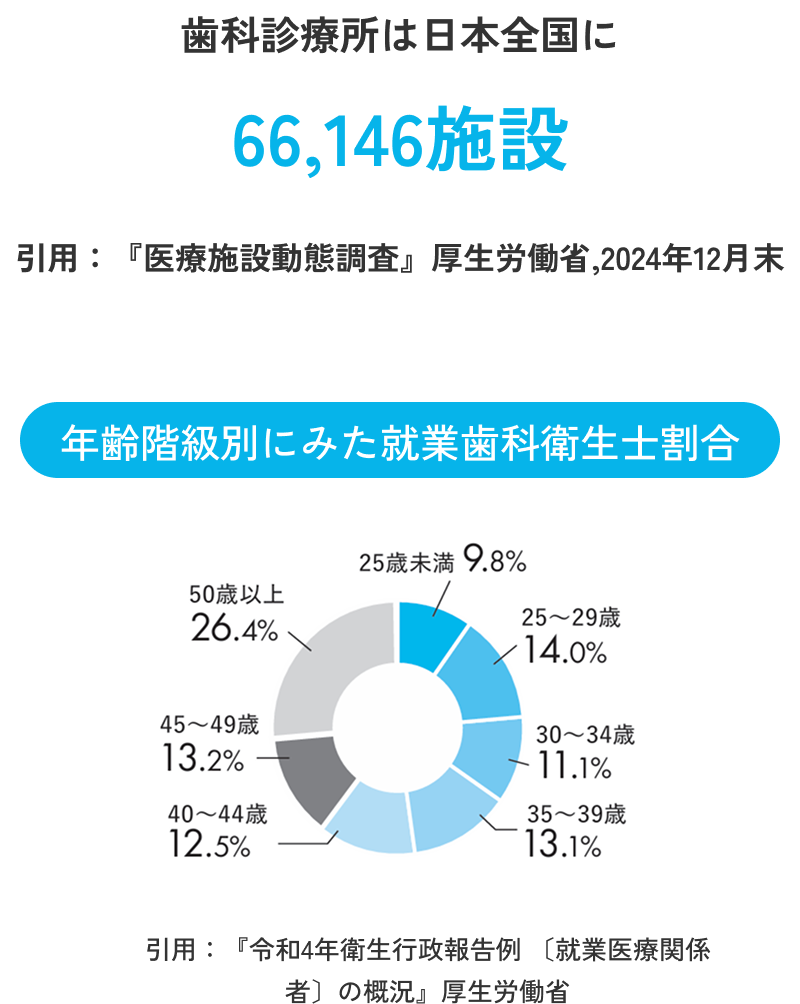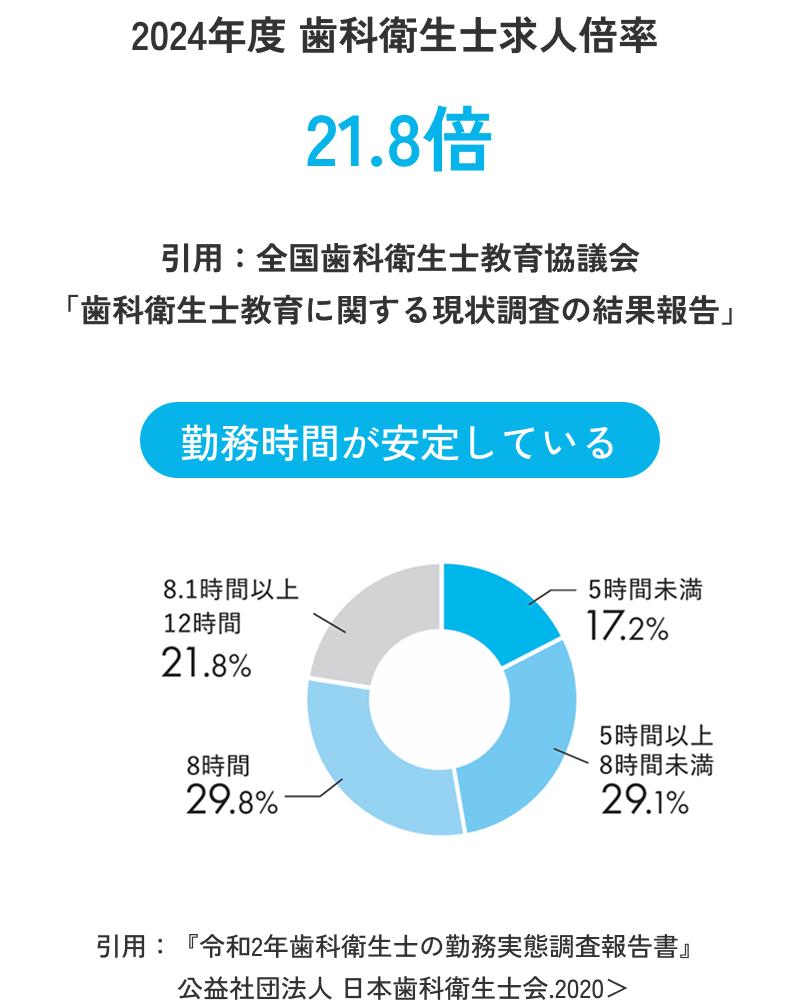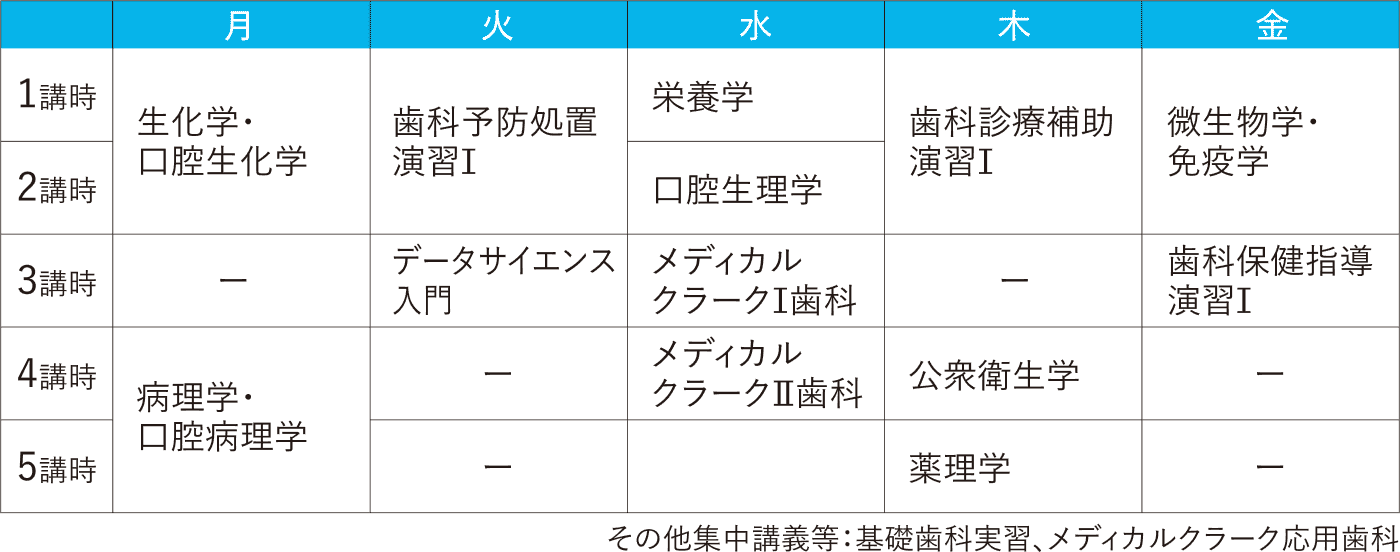ICUから緩和病棟まで、歯科衛生士の活躍の場は無限大です
歯科衛生士として手術前後の口腔ケア、ICUから緩和ケアなど幅広い全身疾患を持つ病棟患者の口腔ケアを行っています。その他、医師、看護師、歯科医師、栄養士など他職種と連携し、患者さんのQOL向上のためチーム回診にも参加しています。このように歯科衛生士はさまざまな職種の方と連携する機会が多いため、歯科分野だけでなく全身疾患や薬に関する幅広い知識はもちろん、円滑に対応できるようコミュニケーション能力を身につけておくことが大切です。歯科衛生士は、病院だけでなく、行政や企業など活躍の場が多く、自らのライフステージに合わせて働けるところが魅力です。