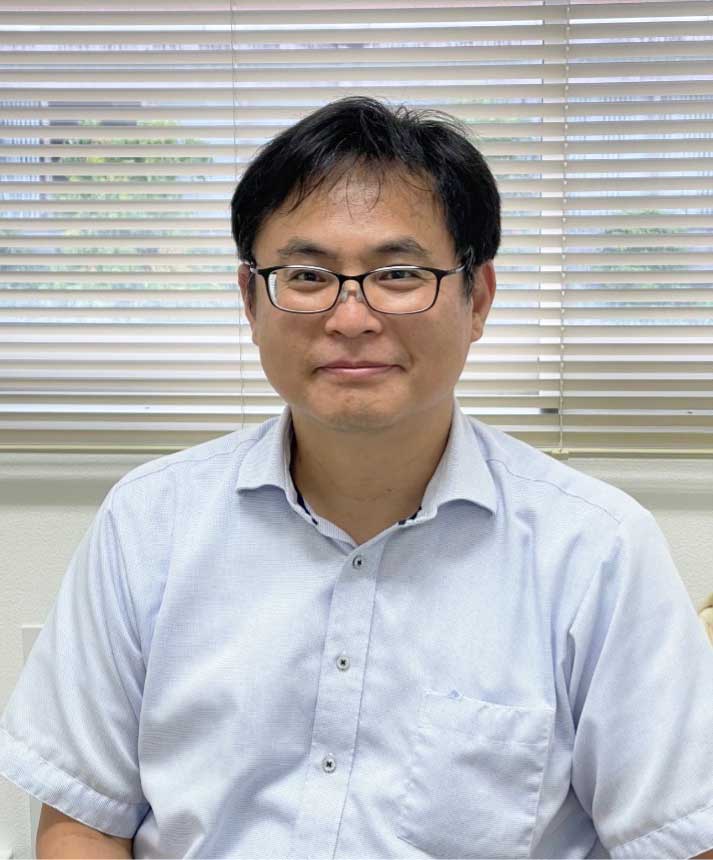2024年4月1日、京都光華女子大学短期大学部歯科衛生学科の教授に着任した稲葉裕明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大阪生まれの大阪育ちの歯科医師です。社会人になってからは大阪から奈良へ。一度大阪に戻り、今度はアメリカ・フロリダ州へ。またまた大阪に戻り、彦根に岡山と巡り、10年ぶりに関西に戻ってきました。趣味はスポーツ観戦、上方落語鑑賞、歴史の勉強に神社仏閣城巡り、と良く言えば『自分磨き』に精を出しているというところでしょうか。専門は口腔微生物学です。お口の中の歯周病菌やむし歯菌がヒトの体にどのような影響を及ぼしているかをテーマに20数年研究し続けています。
「むし歯予防デー」と言えば6月4日。多くのみなさまもご存じかと思います。日本歯科医師会のホームページを見ると、どうやらこれは戦争前のお話のようです。戦後の1947年、6月4日から10日まで「口腔衛生週間」で復活し、今では「歯と口の健康週間」になりました。いずれにせよ、多くのみなさまに少しでもお口の健康に興味を持っていただけましたら、歯科医師として有難い限りです。
むし歯と言えば、なぜ「虫の歯」と言われるのでしょうか?古代ヨーロッパではむし歯の原因は「足の無い虫(ワーム)」が原因と考えられていたとか。紀元前2000年頃バビロニア王朝時代の図書館資料でも「歯の虫」という記述があるようです。それから年代が進み、中国では「牙歯虫候」、日本では「虫長六」と、洋の東西問わず『虫歯=歯にいる虫が原因』と思われていたようです。そのために虫歯と言う言い方になっているのかもしれませんね。ちなみに英語ではdental caries(デンタル・キャリーズ)やdental decay(デンタル・ディケイ)と言って、虫とは関係ない表現です。
虫歯はきちんと歯磨きをし、きちんと歯科医院でメンテナンスを受けているとそれなりには予防できる病気です。とは言え、動画を見るとき、本を読むとき、ダラダラ過ごすとき、みんなとおしゃべりをするとき、おいしい食事や飲み物や甘いお菓子は傍らにかかせないですよね。楽しい宴のあとは、歯磨きも億劫になりがちです。わたしもこの原稿を書きながら、甘いコーヒーにドーナツを片手に書いています。書き終わったら、読みかけの歴史の本を読もうと思います。いや『自分磨き』をしている場合ではありません、歯磨きのお時間です。
CLOSE