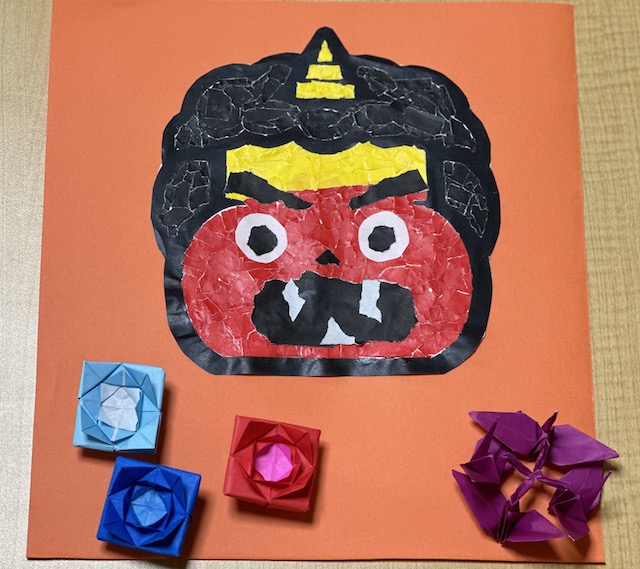皆さんこんにちは?
精神看護学実習では、精神科病院と地域の福祉サービス事業所で実習をし、最終日に学内で学生さんがそれぞれの学びを共有します。
今日はその学びの一部をご紹介します。
?「カルテに書かれていることは、患者さんのほんの一部。
実際にコミュニケーションをとってみないと、
患者さんの考えていること、思っていることはわからない。
だけど、そんな思いを話してもらえる関係性を作るには、
「聞く」だけではなく、自分の思いも正直に伝えることが大切だとわかった。」
?「精神科の患者さんに対して、「怖い」という思いを持っていたが、それは偏見でしかなかった。
一緒にトランプをしたり、みんなで歌をうたったり、
楽しそうにしている患者さんたちを見て、
何も知らないことが「偏見」につながっているのだと思った。」
?「プロセスレコードを書いて、自分の考え方の癖や価値観に気が付いた。
そこに気が付かないでいると、患者さんの見方に偏りがあることに気が付かなかったと思う。
患者さんを理解することは、自分自身を理解することとセットになっていると思った。」
?「患者さんが「できないこと」を「問題」ととらえ、
それをできるようにすることが看護なのだと思っていたが、
それでは患者さんの「その人らしさ」を見失ってしまう。
できないことがあっても、それ以上にできることを伸ばすことが
その人の人生を支えることになる。
そういう大切なことに気づく実習だったと思う。」
?「これまでは、自分の立てた目標を達成することに一生懸命になっていたが、
それは本当に「患者さんのため」だったのかな…と思う。
自分が達成できることではなく、患者さんの思いに耳を傾けて、その人の「~したい」を叶えようとしてこそ、
「患者さんのため」の目標になるんだということに気が付いた。」
写真は、レクレーションで患者さんと学生さんが一緒に作成したものです?
うんと悩んだり考えたりした分、大きな学びを得た実習だったことがわかります?✨
ここでの経験が今後に活かされますように?✨