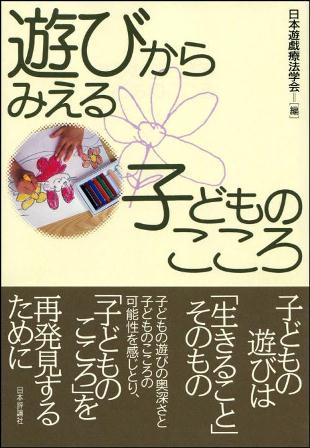【前編からの続きです】
のちに、この保育園にお願いして1歳児の鏡像の前での行動の観察や実験のために約5か月通いました。部屋に大きな鏡を置いた時の子どもの反応はなかなか面白いもので、最初は警戒気味でしたが、そのうち手でさわったり、頬をくっつけたりして近づいていました。そして一歳半ぐらいの子どもたちは鏡像とかくれんぼうしたり、ビスケットをあげようとしたりするなど、自分の分身のように遊びました。自分の映り姿を自分として認めるプロセスには「自分というもの」をどのように捉えるかの段階が含まれています。この時この子どもたちは、鏡の向こう側にいる「子ども」に対して、実態性を感じているとともに「お友だち」のように親しみを感じていることに感銘を受けました。鏡像は決して「ただのイメージ」ではないのです。(もっともフロイトが言うように大人に近づくと鏡像は「不気味なるもの」にもなるようですが。)
私にとっては、子どもが遊びを通して世界や自分を探索して、発見したことを自分の生きる知恵にしていることを身近に体験し、実感として把握できたことはとてもありがたいことでした。
その時子どもにもらったエネルギーは、現在子どもに関わる情熱になっているとつくづく思います。親子教室では子どものお母さんたちにも参加して頂いて、季節に応じたイベント遊びを楽しんでいます。夏は魚釣りごっこ、秋は運動会、冬はクリスマスリースづくりをするのですが、1月から2月には、3月の「お買いものごっこ」に向けてのお楽しみを積み重ねています。お財布づくり、商品づくりでは子どもと一緒になってお母さんたちも遊んでいます。お母さんたちからは子どもとの遊びを楽しむヒントになっていると好評です。今後とも、子どもが成長を重ねていく傍にいたいと思っています。
徳田 仁子(2015年10月21日)
★徳田先生も執筆されている図書のご案内★
日本遊戯療法学会(編)(2014).
遊びからみえる子どものこころ 日本評論社
[Amazonへのリンク]
CLOSE