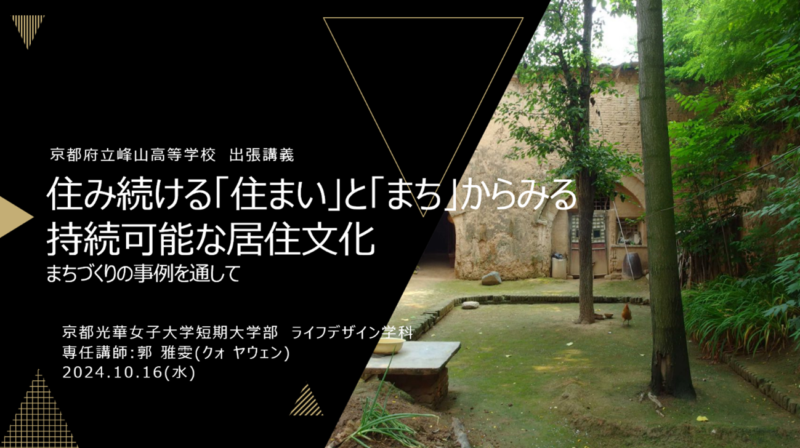ニュース
2024.10.30 専門分野コラム住み続ける「住まい」と「まち」からみる持続可能な居住文化-まちづくりの事例を通して
住居・インテリア分野の授業を担当しております、郭 雅雯(クォ ヤウェン)です。
2024年10月16日(水)、京都府立峰山高等学校に出張講義へ行ってきました。まちづくりや外国の方との交流、伝統の継承やものづくりに興味を持つ学生や、似たテーマを探究学習のテーマにしている学生がいらっしゃることが私にご依頼いただいた理由の一つでした。
今回は、2年生と3年生の学生を対象に、「住み続ける『住まい』と『まち』からみる持続可能な居住文化–まちづくりの事例を通して」という内容で講義を行いました。
世界には実に様々な気候や風土があり、そこで人々が生活を営んでいます。日本の住居や居住文化をより深く理解するためには、国境を越え、視野をさらに広げ、海外の建築、住居、まちを知る必要があると思います。今回は、海外の建築と住居、まちの分析を通じて、地域で各種の自然環境、気候や風土、文化、住み方に適した暮らし方を工夫しながら住み続けていること、地域デザインやまちづくりをどのように行っているのかを知ってもらうこと、暮らしの持続可能性を考えてもらうきっかけになればと思いました。学生の興味関心を引き出した上で、探究学習や地域デザイン、まちづくりの専門性の向上へ繋げればという狙いです!
今回の講義について学生から感想をいただきました。
「それぞれの地域の気候、環境を考慮いた地域デザインはよく考えられていて、そのデザインを考えた人たちは凄いなと思うばかりで、将来私がそっち側の立場になると考えたら、楽しみになりました」「その土地の環境などを考えながら住宅を建てたり、またそれを大切にしながら住んでいることを聞いて、建築やまちづくりについて考える機会になりました」「気候や近隣との関係などを考えながら計画していること、大昔のその時代からまちづくりをされていること、印象に残りました」「日本と世界の空間デザインなど、居住文化が全然違うことが分かりました」「海外の住居について分かり、日本と少し違うところもあれば、全然違うところもありました」「異文化だから排除せずに文化を尊重しながら、自分たちが暮らしやすいように改善していくのは大切なことだなと思いました」「日本のインテリアや造りが影響しているものもたくさんあって、国を跨いで学ぶ面白さも知られました、この講義を聞けて良かったです」
今回の講義が少しでもお役に立ったようで、嬉しく思います。
今回、お招きいただきました北岡先生、高校生と触れ合う貴重な機会をいただき、どうもありがとうございました。