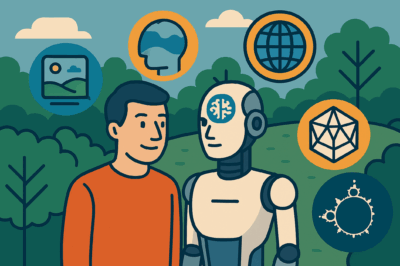ニュース
2025.07.26 専門分野コラム人間の知能とAIの「知能」その3 -多様な知能のあり方-
ライフデザイン学科教員の相場です。
このブログシリーズでは人間の知能とAIの「知能」の関係を考えています。先に進む前に、「その1」「その2」の内容をふりかえっておきます。
「その1」ではロジャー・ペンローズの議論を紹介しました。彼は、人間の知能をアルゴリズムで完全にシミュレートできるかという問題を取り上げます。もし人間の知能をあるアルゴリズムで表現できると仮定すると、そのアルゴリズムには対応する形式的体系(公理系)が存在します。そして、ゲーデルの不完全性定理によって、その体系には証明も否定もできない命題、いわゆるゲーデル命題が必ず現れます。アルゴリズムはこの命題を扱えませんが、人間は「この命題は証明できない」という意味を読み取り、真であると理解できます。これは矛盾です。したがって、ペンローズは「人間の知能はいかなるアルゴリズムによってもシミュレートできない」という結論に至ります。これが「非アルゴリズム仮説」です。ChatGPTにもこの仮説を尋ねてみましたが、いくつかの反論は挙げつつも完全には否定しませんでした。知能については曖昧な議論が多い中、非アルゴリズム仮説は「人間の知能の本質は意味を理解することであり、それはゲーデル命題が真とわかることだ」と明快に定義しており、このシンプルさが魅力です。私はこの仮説をすぐに捨てず、しばらく考察を続けることにしました。。
続く「その2」では、意味の理解と関連して「言葉を操るためには意味を理解していなければならない」という仮定を取り上げました。ジョン・サールの「中国語の部屋」問題を通じて考えた結果、この仮定が正しければ、言葉を自在に操るアルゴリズムは存在しないことになります。ところが、ChatGPTの登場によってこの結論は覆されました。ChatGPTはどれほど複雑であっても単なるプログラムに過ぎません。それにもかかわらず、人間と同じように自然な言葉を操ることができます。これは、先ほどの二つの仮定のどちらか、あるいは両方が間違っていることを意味します。もし非アルゴリズム仮説を捨てないなら、残る結論は「意味を理解していなくても言葉を操れる」ということです。これは非常に衝撃的な気づきでした。
数式処理ソフト「Mathematica」の開発者として知られるスティーブン・ウルフラムも、著書『ChatGPTの頭の中』で同様の見解を述べています。人間にしかできないと考えられていた小論文執筆のようなタスクが、計算処理の観点では意外に“浅い”問題だったことが、ニューラルネットが小論文を上手に書ける理由だというのです。こうして、人間の知能とAIの「知能」は根本的に異なるはずなのに、言葉の運用能力は重なるという不思議な状況が浮かび上がってきました。
ここまでが「その1」「その2」の内容です。
この複雑な状況を整理するヒントとして、最近出会った本を紹介したいと思います。田口義弘著『知能とは何か』です。著者は物理学者で、非線形・非平衡系の研究を背景にこの本を書かれています。
著者も「我々が知的な作業だと思っていたものは別に知能などなくても実行可能なタスクだった」という考えに同意しています。人間の知能のように意味を理解していなくても言葉は操れるということであり、このブログシリーズと同様の考え方です。
そして、これまでの知能研究を次のようにふりかえります。「人類はいままで知能とは人間の知能のことであると考え、知能研究は人間の知能の研究であり、そして人類の知能こそが唯一無二のあり方であり、知能研究=人類の知能研究だという立場でなされてきた」確かにその通りです。そして、人間の知能をAIはシミュレートできるかを問題にしてきたのです。
しかし著者は、生成AIの登場によってこの見方が大きく変わったと指摘します。知能研究はもはや「人間の知能の模倣」ではなく、「世界をどうシミュレートするか」という問題として再定義されるべきだというのです。著者は人間の脳を「現実世界のシミュレーター」と捉え、生成AIもまた異なる原理で現実をシミュレートしている機械システムだと説明します。重要なのは、世界を十分に表現できるシミュレーターは一つではないという点です。つまり、脳や生成AIは数多ある「知能」の実現形態のうち、たまたま二つの例に過ぎません。
さらに著者は、生成AIは意味を理解していないとしつつも、それは雲の生成原理を完全に解明せずとも雲を再現できるモデルがあるようなものだと述べています。異なるダイナミカルモデルが同じ現象を再現できるように、AIも人間と異なる方法で現実を再構築し、言語を操れるのです。そういう意味で知能の可能性は無限に存在します。今後も人間やAIとは異なる新しいタイプのシミュレーターが次々に現れるだろう、と著者は予測しています。
この視点に立てば、私たちが長らく抱いてきた「人間の知能こそ唯一の知能であり、AIがそれをシミュレートできるかが問題だ」という考えは根本から問い直されます。知能とは、人間特有の能力ではなく、世界をどのようにシミュレートできるかという多様な可能性の一つであり、生成AIはその可能性を実際に示した例に過ぎないのです。
私も物理屋だからでしょうか。「生成AIは意味を理解していないとしつつも、それは雲の生成原理を完全に解明せずとも雲を再現できるモデルがあるようなものだ」という考えにはなるほど!と思いました。こうして見えてくるのは、AIが人間の知能を「模倣しているかどうか」ではなく、知能そのものが多様であり、さまざまな形で世界をシミュレートしうるという新しい視点です(ただし、知能そのものが多様であるように再定義したからといって、人間の知能がこれによって解明されたわけではない点に注意が必要です)。
もはや「AIの『知能』」とカッコ付きで書く必要はないと考えます。生成AIは知能のもう一つの実現形態なのです。さらに、今後も私たちが想像もしない新しい知能の形が現れてくる可能性大でしょう。
これまでの議論を踏まえ、このブログのタイトルは次のように変更するのがふさわしいと感じます。
「人間の知能とAIの知能 その3 -多様な知能のあり方-」