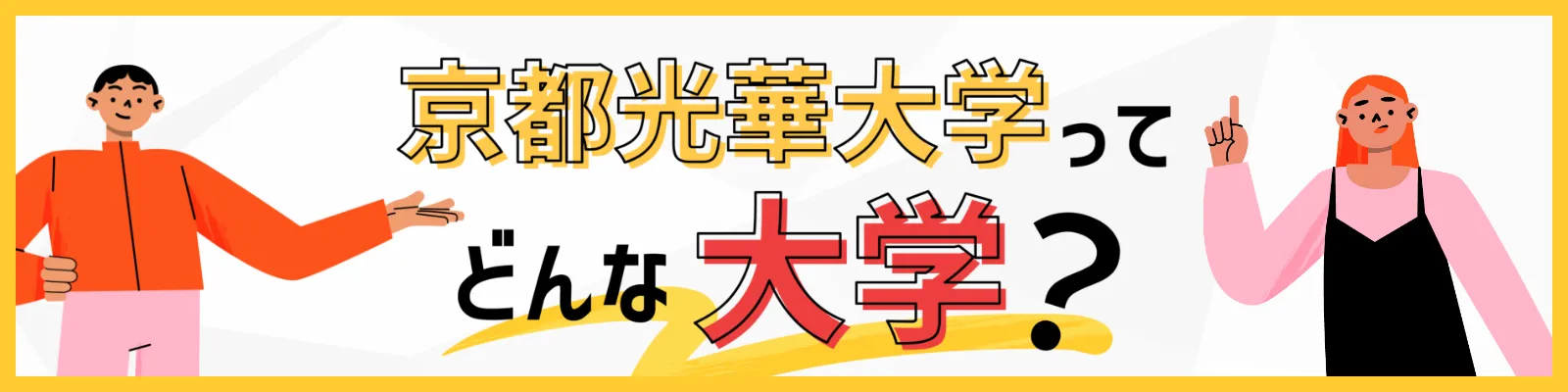教員紹介
教員紹介
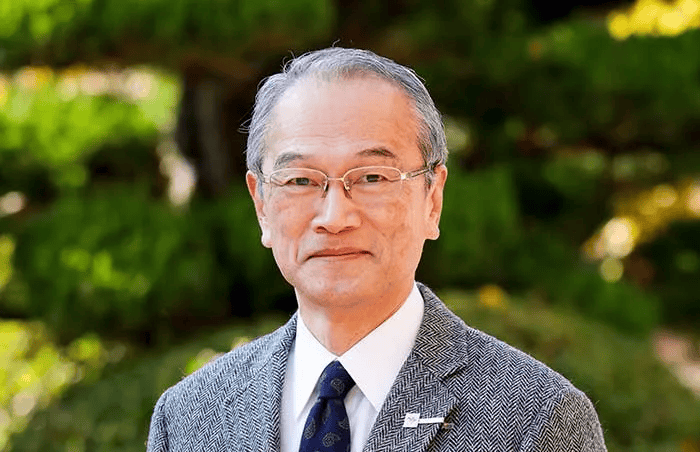
研究テーマ
動物を使った咀嚼、吸啜、嚥下をコントロールする神経メカニズムの研究や、小学生の咀嚼機能の発育、高齢者の咀嚼機能や嚥下機能の低下について研究を行っています。
専門分野の魅力
食べ物を咀嚼する時、下顎だけでなく唇や舌がタイミングを合わせて上手に動き、食べ物を細かく噛み砕いて消化を助けます。しかし食物が細かくなってもバラバラな状態では,うまく飲み込むことができません。咀嚼中に大量に分泌される唾液と混ざり合うことで一つの食塊となり、嚥下しやすくなります。口の機能である咀嚼や嚥下が正常に働くことは、バランスの良い栄養摂取につながり、子どもの健やかな成長や高齢者の健康維持に欠かせません。さらに、食べ物を咀嚼することで、その風味を楽しみ、食事の満足感が高まります。口は単なる器官ではなく、私たちの健康と豊かな生活を支える重要な存在なのです。
高校生へのメッセージ
"歯がむし歯や歯周病で抜けても、すぐに体調が悪化して入院することはありません。しかし、栄養摂取のバランスが崩れるため、長期的には健康に影響を与える可能性が高まります。また、嚥下機能が低下すると、食べ物が食道を通らずに誤って肺に入り、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。日本では、誤嚥性肺炎による死亡者数が交通事故による死亡者数を上回っています。
歯科衛生士として、お口の健康を守ることは、人々の健康維持に欠かせません。咀嚼や嚥下を支えることで、栄養のバランスを保ち、誤嚥性肺炎などのリスクを減らすことにもつながります。目立たない仕事かもしれませんが、健康に過ごせる社会づくりに貢献できる、とても大切な役割なのです。"