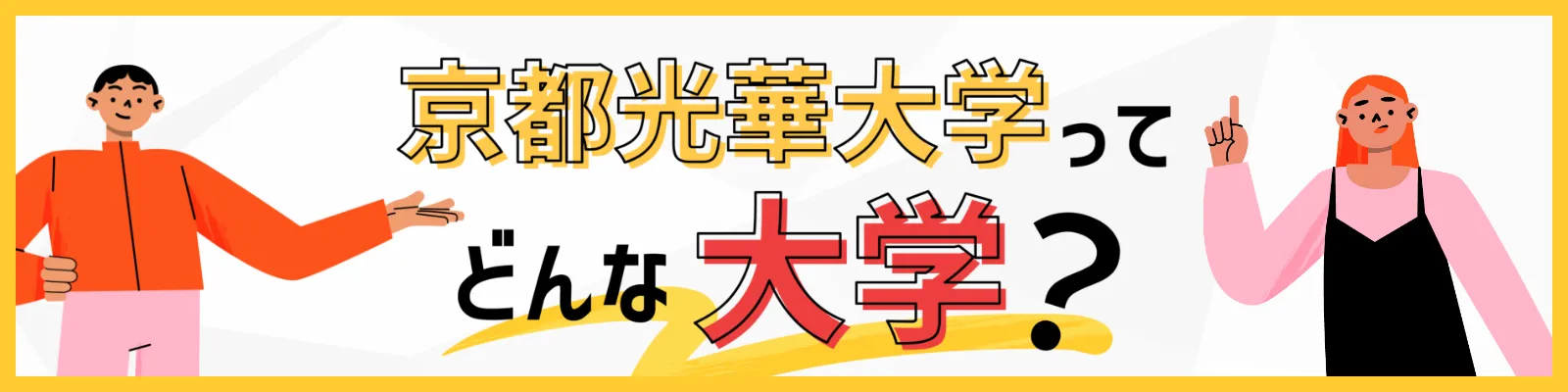社会共創パートナー
本学は、グローバル化、デジタル化、少子高齢化といった社会の変化に対応し、誰もが心身ともに健やかに暮らせる“Well-Beingな社会”の実現を目指しています。
そのため、地域社会や企業、団体など、様々なステークホルダーの皆様と連携し、教育改革を推進するとともに、本学が目指す「すべての人の幸せに”つなぎ・つながる・つなげていく”社会」の実現に向けた活動を幅広く展開しています。
この理念を実現するため、本学では「社会共創パートナー」という形で、共に未来を創るパートナーシップを築いてまいります。
教育・研究活動における連携、地域社会への貢献活動、人材育成など、多岐にわたる分野で協力し、「社会共創パートナー」の皆さまと共に、Well-Beingな社会の実現に向けて歩んでまいります。
京都光華が目指す「共創」とは
「共創」という言葉は、「共に創る」という意味を持ち、それぞれが持つ違いを認識し、互いの知識や能力を掛け合わせながら、個人や組織単独では実現できない価値を生み出すプロセスを指します。さらに本学では、建学の精神に基づく自己の内省を通じて他者を深く理解すること、多様性を尊重しながら支え合うことを大切にしています。そうした理念を基に、多様な人々と協働し、共に新たな価値を創造することを京都光華の「共創」と定義しています。

社会共創の事例
「光華ワクワク×健やかフェス」の開催
地域交流の場として本学を開放し、「健康・未来創造キャンパス」の実現に向けた教育・研究活動を紹介することを通し、地域にお住いの方が「来場された時よりも健やかでワクワクした気持ちになれる1日」というコンセプトのもと開催しています。当日は幅広い年齢層の方々にお楽しみいただけるような催し物や体験イベントを実施。本イベントは本学だけではなく地域のさまざまな団体・企業・組合様とともに作り上げています。
詳細はこちら

「光華こども食堂」の開催
こどもの居場所づくりを目的に、新たな地域交流の場として本学主催の「こども食堂」を開催しています。プロジェクトには「栄養」や「福祉」「こども」に携わる学生を中心に本学のさまざまな学科の学生が参加しています。単に料理を提供するのではなく、食育要素を取り入れた遊びを行うなど、学生たちの日頃の学びを生かした交流企画を実施しています。また、JA京都中央様から規格外野菜を提供していただくなど、フードロスの削減も意識して、こども食堂の運営を行っています。
詳細はこちら

関連リンク
社会共創パートナー一覧(122社)
※2026年01月09日現在
五十音順
-
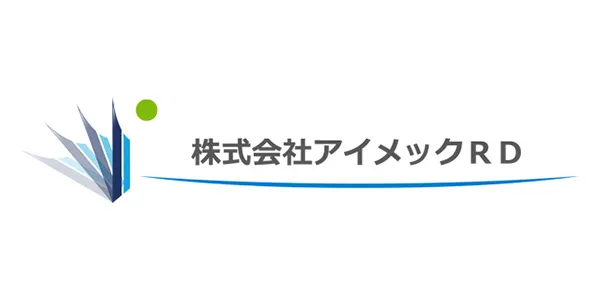
-
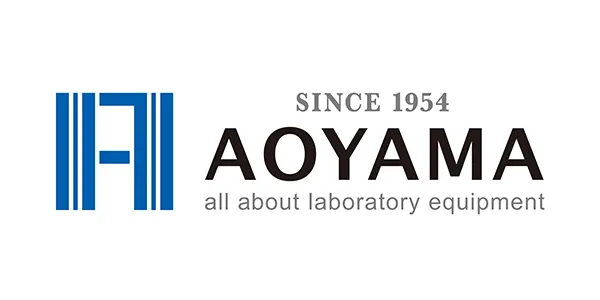
-

-

-

-
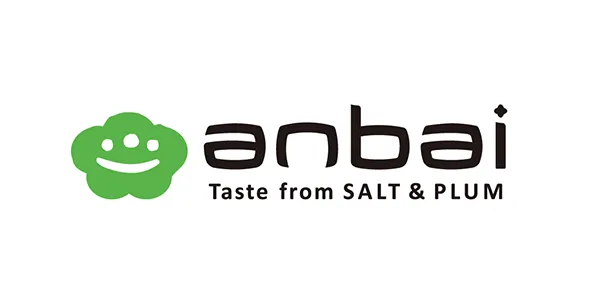
-
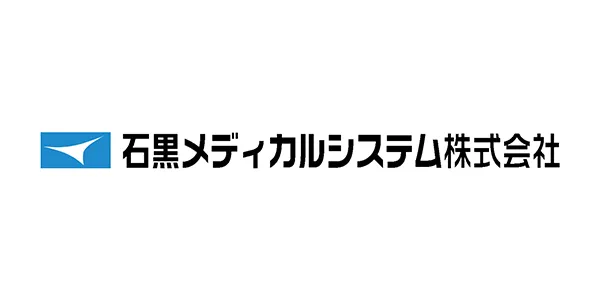
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
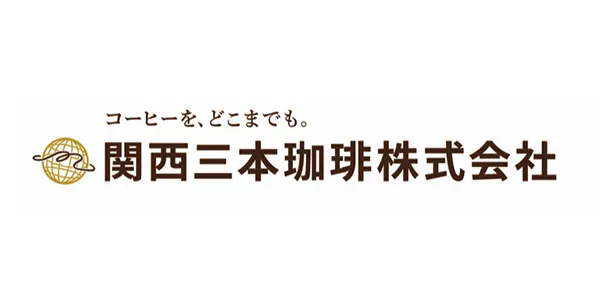
-
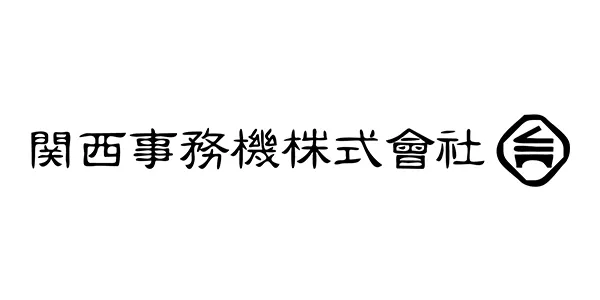
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

学際研究所 がくさい病院 -

-
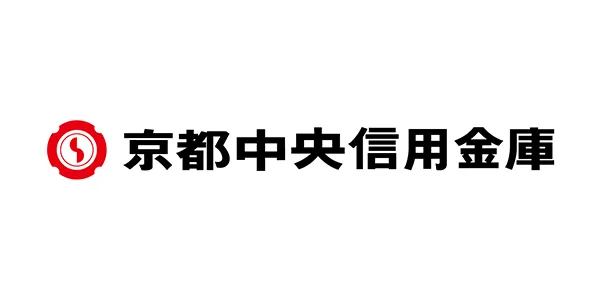
-

-

右京支部 -

京都難病支援パッショーネ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

グローカル人材開発センター -

-

-

-

-

-

-

子育ては親育て・みのりのもり劇場 -

-
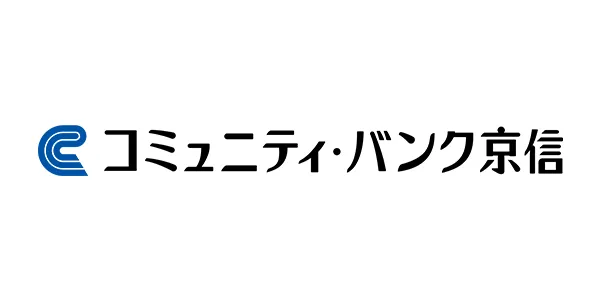
-

-

-

-

-
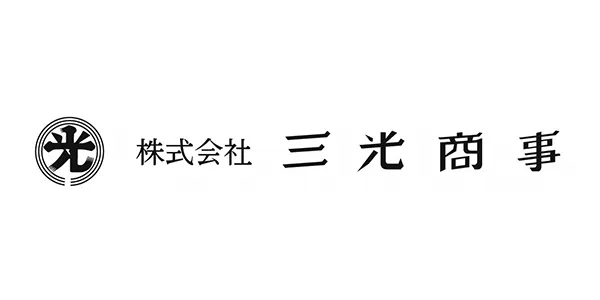
-

-
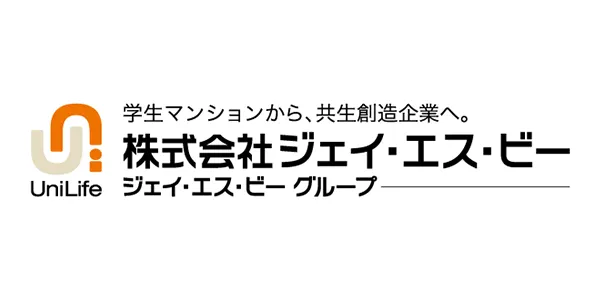
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
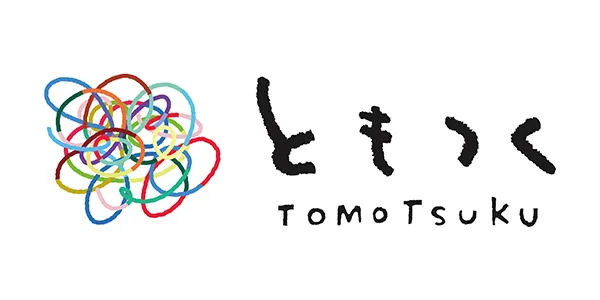
地域共生開発機構ともつく -

-

-

-

-

-

-
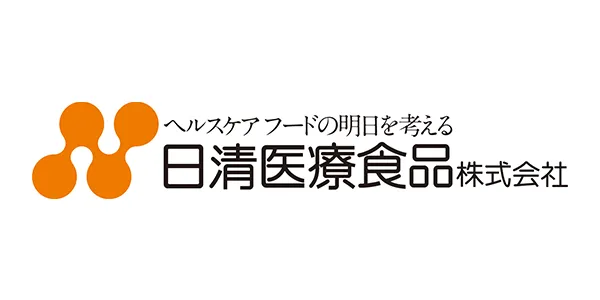
-

-

右京支部(西空会) -

-

-

京都〈ゆうゆうの里〉 -

-
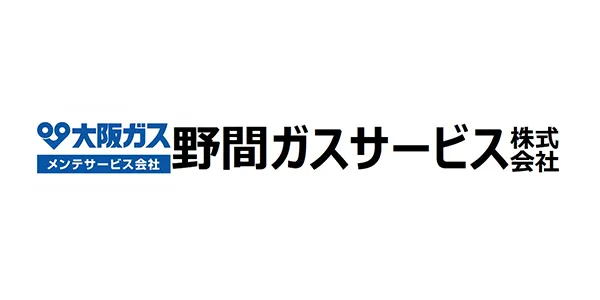
-

-

-
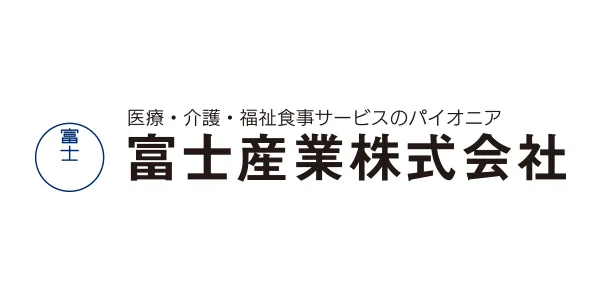
-

-

-

-

-

(南興業株式会社/阪急阪神第一ホテルグループ) -

-

-

-

-

-
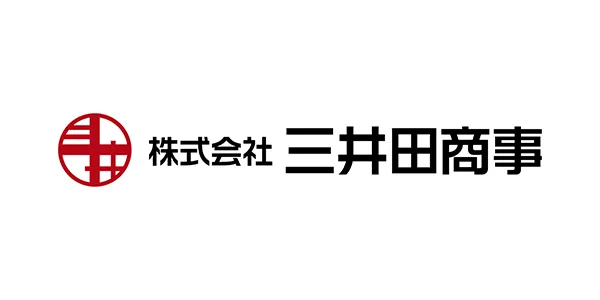
-

-

-

-

-

-

-
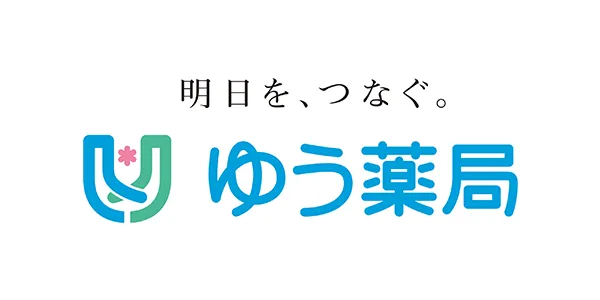
-

-
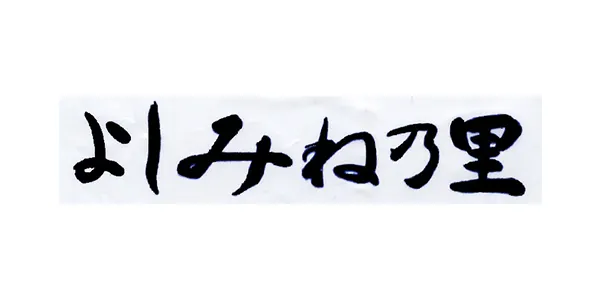
-

-

-

-

-

お問い合わせ先
京都光華女子大学・
社会共創パートナー事業推進チーム
〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町38
career@mail.koka.ac.jp
担当:小椋・橋詰