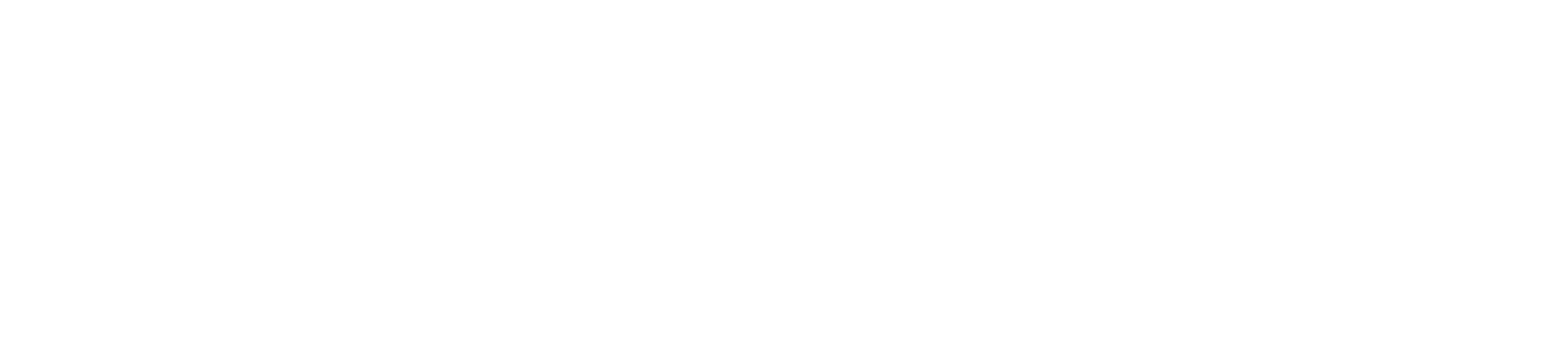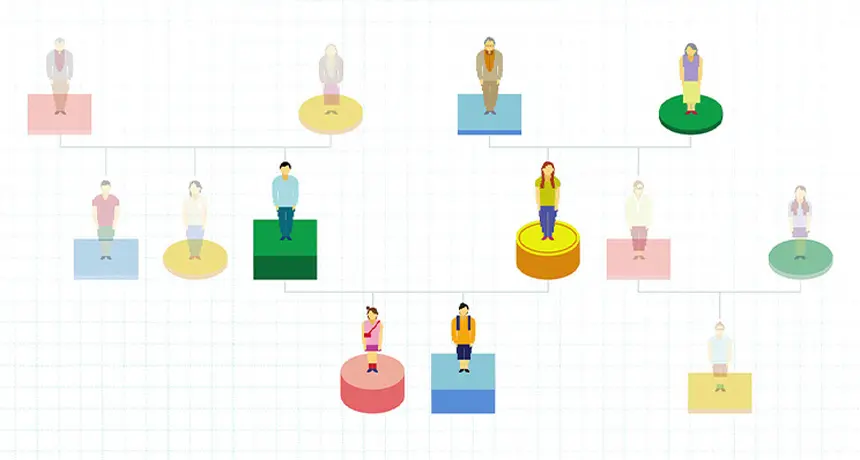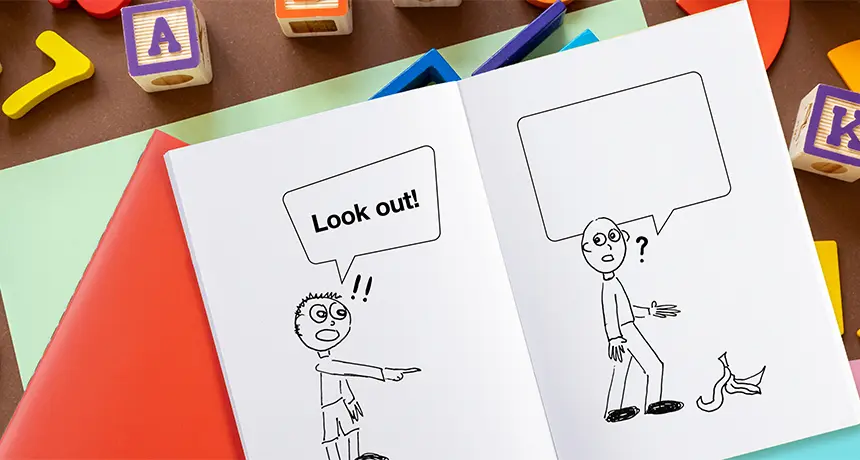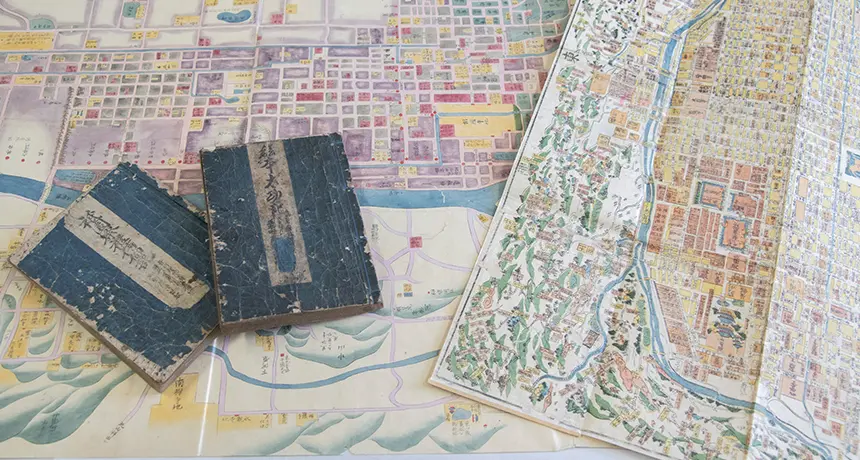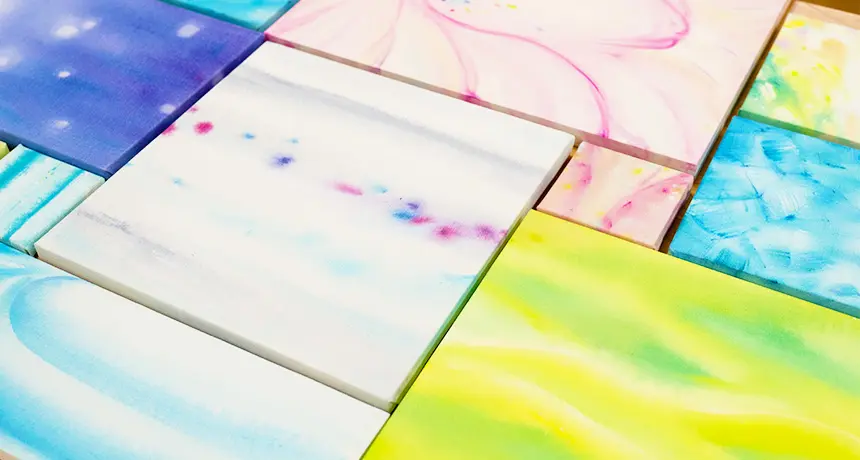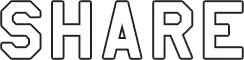何度でもチャレンジすることが「レジリエンス」を育てる
東日本大震災後の経験から
人は本来、ストレスをはね返すしなやかな心を持っているものです。「立ち直る力」と言っても良いでしょう。心理学で「レジリエンス」と呼ばれるその力は、どうすれば育てられるんだろう。そう考えて研究と実践を行っています。
東日本大震災の後、スクールカウンセラーとして福島県に派遣され支援活動を行った時のことです。家族を亡くしたり、家を失ったりして大きな悲しみやストレスの中にいる子どもたちにも出会いました。なかには「あの時自分がこうしていたら」と自責の念にかられている子もいました。そんな中、1カ月くらいたつと、つらいながらも前向きに進みだそうとする子と、ずっとつらい気持ちが続いてPTSD(心的外傷ストレス障害)のようになっていく子が出てきました。つらく苦しい気持ちは誰しも一緒ですが、立ち直り方に違いがあるのはなぜかと考えたのが、レジリエンスという考え方との出会いでした。レジリエンスは誰もが持っているものですが、それが豊かに育っているかどうかによって、ストレスを受けた後の立ち直り方が変わってくるのです。


失敗の経験も「レジリエンス」を育てる
レジリエンスを育てるには「土台作り」と「考え方」が大切だと私は考えています。
「土台作り」とは、レジリエンスを構成する以下のような要素を自分の中にしっかり持つことです。
自尊感情:自分を尊重してもらえる、受け入れてもらえるという気持ち。
自己効力感:自分は存在するだけで認めてもらえるという気持ち。
感情のコントロール:怒りや嫉妬などマイナスの感情もしっかり感じた上で、適切に表現できること。
楽観性:「なんとかなる」という気持ち。
人間関係:落ち込んだ時に話せる人がいるかどうか。
また、すべての土台は人との関係の中での経験によって培われます。
「考え方」とは、自分のネガティブ思考のくせを客観視することです。人は誰もがその人特有の「マイナスの思い込み」を持っているものです。たとえば、「自分の正義感に合わない態度をとる人にイライラする」「先のことについていつも漠然と不安を感じる」「自分の欠点ばかりが気になる」などの思い込みです。自分にはどのようなクセがあるかをまずは客観的に認めましょう。その上で、自分にできる対処法を実践するのです。思い込みを捨て去る、気にしないということができれば良いですし、時には違うタイプの人の持つ視点を取り入れながら、自分のネガティブ思考を客観的にコントロールできるようになると良いと思います。
また、適度に運動をして良質の睡眠をとるといった生活習慣も大切です。また、没頭できるほど好きなものがあるということもレジリエンスにつながります。そして、自分のやりたいことにチャレンジしましょう。「百戦錬磨」という言葉があります。何度もチャレンジして、何度も成功と失敗を味わっているからこそ、経験が豊かになり、さらにレジリエンスが育てられていくのです。

親子関係の中で子どものレジリエンスが育つ

親子教室や子育て相談での実践を通して
小さな子どものレジリエンスは、主に親子関係の中で育てられていきます。親としっかり向き合い、一緒に遊ぶと楽しいと感じることで、自分は存在価値がある、大切にされている、助けてもらえるという自分への信頼、人への信頼、世界への信頼が育まれるからです。
でも最近は子どもと一緒に遊ぶことがあまり上手ではなくなっている親もいます。本学併設のカウンセリングセンターでは、2008年から「ひかりっこ*くらぶ」という親子教室を開催しています。地域の子育て支援の一環として始まったもので、私たち臨床心理士や公認心理師がファシリテーターとなり、絵本の読み聞かせやものづくりを楽しみながら、親子で一緒に遊び、他の親子と交流する機会を提供するものです。
思った通りにならない子育てでイライラしたり孤立感を感じたりしている親御さんに、日常から離れ、安心できる場所でゆったり子どもと遊ぶことによってホッとしてほしいと思っています。親の心が安定することが、子どものレジリエンスを育てることにもつながるからです。また、親のグループでの子育て相談「こもれびスペース」も開催しています。子育ての悩みを専門家に相談したり、他の家庭と体験談を共有したり、テーマに沿って子育てについて話し合ったりすることで、子育ての悩みを軽くしてもらえたらと考えています。
究め人のサイドストーリー
大学時代に合唱をしていました。卒業後は長く歌っていなかったのですが、4、5年前に「ノイエ・ハルモニア」という混声合唱団に参加し、再び歌うようになりました。専門的な指導を受けられるので勉強になりますし、とても楽しいです。京都合唱祭をはじめさまざまなステージに出演するほか、高齢者施設への訪問なども行っています。
声は、磨けば磨くほど人の心に伝わるようになるのが面白いところです。実は、カウンセリングでも声の調子や出し方はとても大事で、心地よい声、安心できる声を目指して磨いていきたいと思っています。

スクールカウンセリングの実際について学ぶ

臨床では社会性や人間性も大切
私が担当する「教育臨床心理学」は、スクールカウンセリングについて学び、不登校やいじめなど学校現場特有の問題について考える科目です。学校で起きている問題を動画などで学んだ後、少人数で話し合い、その内容を全員でシェアします。学校で経験したことやニュースなどで身近にある問題なので、とても熱い討論になります。私がスクールカウンセラーとして直面した問題や実践していることも紹介します。
たとえば、不登校の子どもの場合、「なぜ学校へ行かないのだろう」を考えるのではなく、「なぜ学校に行くのだろう」ということから学び、考えるのがこの授業の特徴です。不登校の子は、学校に行けないからこそ、学校のことが気になる日々を過ごしています。不登校の子にとっての学校の意味は、登校している子とどのように違うのかを考え、話しあうのもポイントです。
授業としては、先に話した親子教室で実習を行う「心理学実践演習」もあります。心理学の知識やスキルを相談援助活動に応用することを学ぶ科目です。子育て相談の「こもれびスペース」では親が話し合っている間、ファシリテーターと共に学生が子どもと遊ぶのですが、学生のほとんどは小さな子どもと初めて接します。しかも人見知りが強く親と離れて泣きわめいている赤ちゃんも多いですから、必死でなだめても手に負えず苦労します。しかしある時、学生の一人が「泣くのにとことんつき合おう」と覚悟を決めて接したら、赤ちゃんがその学生を信頼し、もたれかかって眠ったことがありました。それは赤ちゃんにとっても大きな経験です。初めて出会った学生を信頼して絆を結べたのですから。このように子どもも学生もさまざまな経験をしながら多くのことを学んでいきます。
臨床心理の分野の仕事は、専門性に加え、社会性、人間性も必要です。自分から子どもや保護者に話しかけていく社会性、この人だから相談したいと思ってもらえる人間性を育てて身につけてほしいと思います。たとえ将来専門外の道に進んだとしても、大学で学んだこと、経験したことを、自分の子育てや、地域で生かすことができると思います。

この分野が学べる学部・学科
看護福祉リハビリテーション学部 看護学科
建学の精神であるおもいやりの心を大切にする仏教精神に基づく看護教育が特徴。看護師に加え、保健師の国家資格や養護教諭の免許の取得を目指すことも可能です。
看護福祉リハビリテーション学部
福祉リハビリテーション学科 社会福祉専攻※
支援が必要な子どもに対応できる保育士、医療ソーシャルワーカー、福祉職公務員、3つの進路に合わせ、あらゆる年代の人々の暮らしのしあわせを支えるソーシャルワーカーを育てます。
※2025年度以降 学生募集停止
看護福祉リハビリテーション学部
福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻
ことばや聞こえ、飲み込みに障がいがある人を支援するリハビリテーションの専門職「言語聴覚士」を養成。現場で活躍するプロから学び、臨床実習などを通して各専門職と連携しチーム医療に応えることのできる人材を育てます。
健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻
給食施設や病院での臨地実習により、確かな知識と実践的な技術を身につけます。食と栄養の専門職として社会で活躍できるよう、国家試験合格を目指します。
キャリア形成学部 キャリア形成学科
「経営学・データサイエンス」「生活科学・観光・デザイン」「現代社会学・地域公共」から専門科目を自由に選択して学ぶことで、幅広い知識とスキルを身につけ各種業界の総合職や公務員を目指します。
短期大学部 歯科衛生学科
こどもから高齢者まで、すべての人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする専門職「歯科衛生士」を養成。歯科衛生士として必要な知識や技能を習得するとともに、一人ひとりの健康に寄り添える教養と態度を身につけた人材を育成します。
助産学専攻科 [1年課程]
産科医療の高度化・多様化に対応し地域母子保健を支える実践力を身につけ、女性やその家族と喜び・苦悩を分かち合える、おもいやりの心を持った人材を育成します。