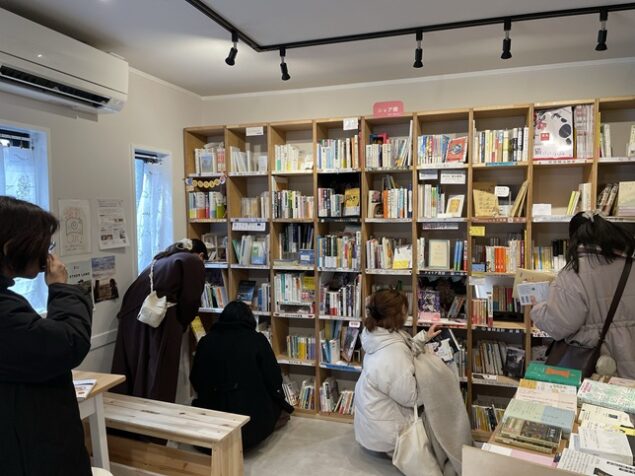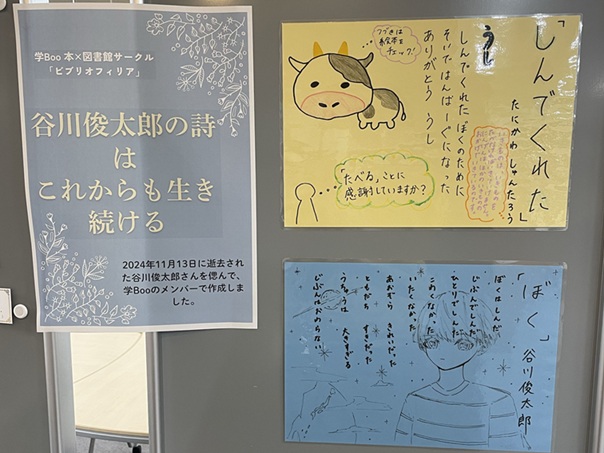2025年3月11日
本学では「王朝衣装」として、平安時代以降の公家の女性の晴れ装束である女房装束(唐衣裳装束=十二単)」と、公家の男性の装束である束帯・直衣・狩衣などを所蔵しています。昭和56年、京都の大学ならではのホンモノの装束をと当時の短期大学家政科の野上俊子教授が中心となり、風俗史の第一人者 江馬務先生の監修のもと、葵祭をはじめとする装束の制作をされている黒田装束店で誂えたものです。装束はもちろん、冠、烏帽子・檜扇・平緒、襪(しとうず:後世の足袋)などすべて有職故実(ゆうそくこじつ)に則った大変貴重なものです。
今回は、本学同窓会(ふかみぐさ 京都支部会)総会(10/27)で披露されるこれらの王朝装束の前日準備10/26に参加させていただき、現物に触れ、十二単の着装の仕方を見学しました。
十二単の着付け(衣紋)は、小袖と長袴の着装の後、2本の紐のみを使い着装します。1枚着付けるたびに下になっている紐を引き抜き、単衣、五つ衣、打衣、表着、唐衣の順に重ね着を整えて、最後に裳を後ろに引き、背中に当てた大腰から繋がる小腰を正面で結ぶ際に着付けに使った紐を引き抜き、小腰ですべての装束を安定させます。この着付け方は平安時代から継承されている衣紋道(山階流、高倉流)により、衣紋者2名が着付けてもらう人(お方さま)への礼儀をわきまえた美しい所作で臨むものです。この回では正式な衣紋の見学ではなく、装束の構成、織物1枚1枚の美しさの上に、日本の四季折々の自然にみられる草木を手本として取り入れた襲(かさね)色目の優美さを初めて見せてもらい、また羽織らせていただき、その気品のある美しさを実感しました。
併せて、数々の男性装束や装飾品、資料を見学し、王朝装束が伝える日本人の感性に触れることができました。
次回は、十二単について、より詳しく学ぶ予定です。